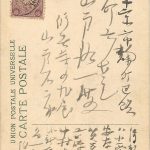山方氏のルーツを調べてみますと、関東管領家となった上杉家、大化の改新にて歴史に名をなし天皇家とも密接なつながりを持った藤原鎌足を祖とする藤原氏の支流・高藤流の末裔です。
山方氏の歴代当主並びに系図につきましては『歴代当主』の項でご確認下さい。
山方氏の興り

山方氏をはじめて名乗ったのは、上杉憲利とされていますが、初代となったのは、その息子の山方盛利です。
茨城県山方城(御城)で配布されている説明によると、
山方氏は藤原鎌足を祖とする藤原氏の末流に高藤流という支流があり高藤の末裔重房が丹羽国何鹿郡上杉庄を領しはじめて上杉氏を称し足利将軍に仕え次第に勢を得て関東管領家となり鎌倉に威を振るいましたが、その一族憲利は美濃国山方郡を領しはじめて山方氏を称しました。
この憲利の子盛利は鎌倉において高梨某と争いこれを殺して逃れ同族上杉憲定を頼って武蔵国にかくまわれていました。
丁度その項太田佐竹義盛に男子がなかったので憲定の子義憲が養子となり常陸へ下向することになったのでこの盛利が選ばれてその傅役としてまた後見人として義憲に供奉して太田に来り佐竹の重臣に加えられ山方御城の館主として山方に封ぜられたのであります。そして盛利を初代として以後七代に亘り代々能登守を称し佐竹の為に忠勤を励みました。
とあります。
この文章だけでは判りづらいので、もう詳しくみてみますと、
1.第十一代当主・佐竹義盛に男児がいなかったため、
2.関東管領上杉憲定の次男・義憲(後の佐竹義人)が佐竹家への婿養子として
常陸国に下ることになり、
3.山方盛利が傅役(後見人)として佐竹家に仕えることになった
ということになります。
この説明からもわかりますが、山方氏が歴史上に名を連ねはじめたのは、佐竹氏の重臣
(守役)として、常陸国に下った頃からとなります。
参考文献:山方城配布資料 ~山方城と山方氏~